乱数製造器としての確率変数
- 標準正規分布に従う乱数を作ってくれる製造器を標準正規分布確率変数と呼ぶ(と呼ぼう)
- このように、問いかければ、何かを返してくれるもの、返してくれる何かが問いかけのたびに変わるもの、ただし、そこにはルールがある、そんなものが確率変数(としよう)
- 一般的な1次元実数確率変数としては、一様分布に従う乱数製造器などなど、ある
- 指数分布に従う乱数製造器も確率変数。これは、ちょっと面白い性質があって、ポアソン事象を連続して観測した時の、2つの事象の間の時間・距離がとる分布になっている
- 何が面白いかというと、「ある乱数製造器が作った、2つの距離」になっていること
- 乱数製造器は1つずつの乱数を独立に作ってくれるのにも関わらず、2つの乱数の距離になっている・・・1つなのに、2つ
- こんなことを考えていた
- 量子確率論では、行列が確率変数になっている
- 行列をグラフの表現と見ると、グラフが確率変数になっている、とも見える
- グラフがあった時、そこから、どんな乱数が製造できるだろうか?
- ランダムに2点を取った時、2点間のグラフ距離はばらつく。この2点間グラフ距離のランダムな分布を作る製造器としてグラフを捉えれば、そのグラフはそのような距離分布をランダムに作ってくれる乱数製造器であり、そのような確率変数を体現していることになる。グラフ距離行列を作成し、そのセルの値をランダムに取り出せば良い(この極限が取れれば、曲面を乱数製造器とみなすこともできる)
- 量子確率論では、グラフの隣接行列を取り、その冪乗の標準化トレースをモーメントとする確率変数としてグラフを考える、という「定番」の確率変数がある
- これは、k-次モーメントを、k歩で、元の頂点に戻ってくる歩道の数の平均値とするような確率変数として、グラフ隣接行列を見よう、ということ
- グラフを乱数製造器とみなすなら、他にも色々できそうだ
- k歩が気になるなら、任意の頂点ペアについて、k歩で行きあえる歩道の数というのも確率変数になる
- さらに、k歩にこだわるなら、k歩進んで、結局、グラフ距離としてどれくらいの所にあるか、というのも確率変数になる
- グラフのゼータ関数は、non-backtracking cycleに関する関数だが、non-backtracking cycleの長さに着目した確率変数の性質を考えていることだとわかる
エッセンス:量子確率論
- こちらで「量子確率論とその応用」をぱらぱらめくった
- 文書を抜き書きしただけで、特に数式についてはあえて端折った
- この記事では、数式関連の抜き書きをする
- 直交多項式は以下のような漸化式で表される
- ここで、
がヤコビ系数列
- ヒルベルト空間の正規直交基底
があって、それらは、3つの作用素によって以下のような関係にある
- また、次のような関係がある
- で、モーメントは
- Rのorthopolynomパッケージを使うと、直交多項式が作れる
library(orthopolynom) p.0 <- polynomial( c( 1 ) ) n <- 10 # ckpk+1 (x) = (dk + ekx) pk (x) − fkpk−1 (x) # rec should specify ck,dk,ek and fk # p_(n+1) = (x-alhap_n) p_n + w_(n-1) p_(n-1) が作りたい rec <- data.frame(c=rep(1,n),d=-rnorm(n),e=rep(1,n),f=runif(n)) p.list <- orthonormal.polynomials( rec, p.0 ) p.list x <- seq(from= -1,to=1,length=101) ys <- polynomial.values(p.list,x) ys.mat <- matrix(unlist(ys),ncol=length(p.list)) matplot(x,ys.mat,type="l")
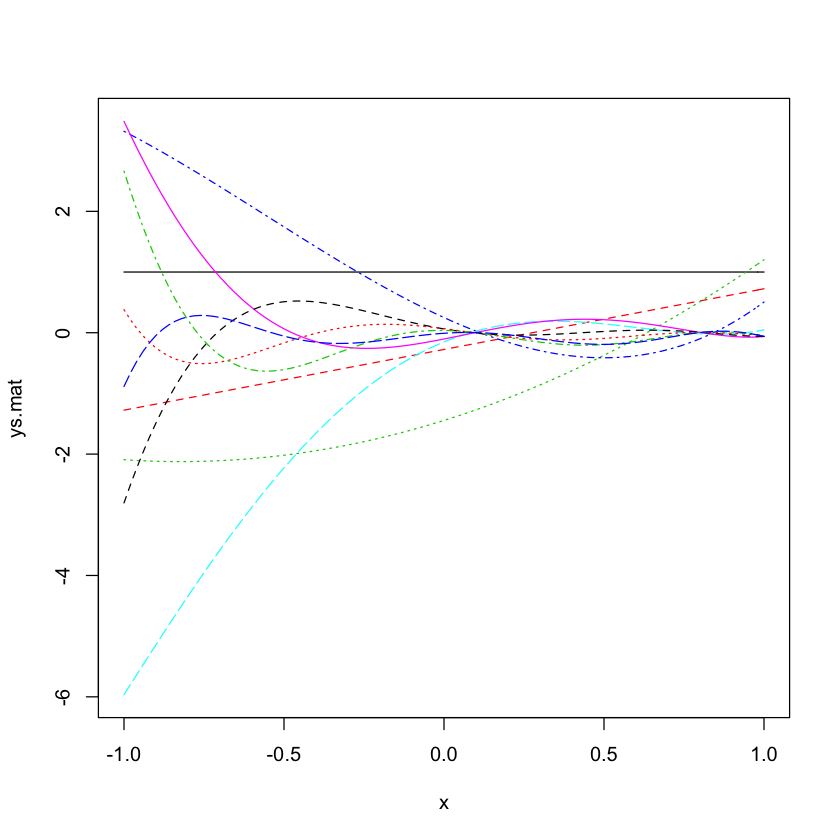
- こんな問題設定
d <- 3 R <- GPArotation::Random.Start(d) V1 <- rnorm(d) V2 <- rnorm(d) sum(V1*V2) IP1 <- matrix(V1,nrow=1) %*% R IP2 <- matrix(V2,nrow=1) %*% R sum(IP1 * IP2)
> sum(V1*V2) [1] -1.460819 > IP1 <- matrix(V1,nrow=1) %*% R > IP2 <- matrix(V2,nrow=1) %*% R > sum(IP1 * IP2) [1] -1.460819
- より具体的には、区間を決めて、その範囲で定義した多項式を使う(ことが多い)。Legendre polynomialsはその一例
ぱらぱらめくる『量子確率論とその応用』 再び
- このPDF『量子確率論とその応用』は、1年ほど前に、読みかじったのだが、消化不良だった。
- 再読を試みる異にする
- いつものごとく、自分の興味・目的に引きつけて読む事になるが、1年前と今とで、何が違うかというと、行列の集合を比較することへの興味が強くなったことだろうか
- 例えば、こちらのarXivペイパー(Comparing lar-gegraphs based on quantum probability theory)のようなことに対する具体的興味が強くなっており、それが、今回の再読の動機になっている
- このarXivペイパーを簡単に紹介すると…
- グラフの行列表現として隣接行列を考える。グラフ・スペクトルによる、グラフ間の異同の評価は、行列の固有値列の比較にすぎなくて、弁別力が不足している
- それは、量子確率論でいうと、正方行列Aが会った時に
を考えるのだが、そのトレースだけを気にしているのでは、固有値セットのみが情報量の全てになってしまうところ、
のトレース以外を取り出す(トレースを取り出すのも、トレース以外を取り出すのも、量子確率論では、状態と呼ばれる関数の仕事なので、「量子確率論の状態」を切り替えることに相当)ことで、Aの持つ情報を豊かにできることを書いている
が何を表すかをグラフに即して少し補足すると、
は、頂点iから頂点jへのk歩の行き方の場合の数。したがって、
を使った量子確率論的k-次モーメントは、2頂点間のk歩パスの数の期待値となる
- このように、確率変数の「モーメント」に具体的な意味が見えてきたことで、量子確率論の枠組みで考えることへの興味が一新された、とそんなところ
- さて。再読
- 目次
- 1 量子確率論の基礎概念
- 代数的確率空間
- *-代数とその上で定義された状態の組
が代数的確率空間、ただし、
は*-代数、
は状態と呼ばれる関数で、
- ここで、具体的なものがないとイメージが湧かないので…。*-代数の好例は、複素正方行列全体、状態の例としては、行列を引数にして、その標準化トレース(トレースを次元で割ったもの、以下、Trは標準化トレースを表すものとする)を返す関数がある。ちなみに、量子確率変数の中に、実確率変数が含まれるが、実確率変数は、複素行列のうち、エルミート行列に対応する
- 「確率」っぽさはどこからくるかと言うと:状態と言う関数は、*-代数の要素
に対して
となると言う条件がある…これが、「至るところで正」であると言う確率っぽさをもち、
(単位行列
)と言う性質は、
をk-次モーメントを返す関数だと見た時に、
となって、全確率を足すと1、と言う確率変数っぽさをもつ、この2点、か。
- 状態に純粋状態と混合状態とがあると言う概念は、量子統計力学的な側面の印象がある
- 複素正方行列を*-代数とする状態には、密度行列が1対1対応する。
。この密度行列は正定値行列であって、
になると言う。後者は
から要求される。前者は「至るところで正」であると言う確率っぽさの条件に対応する
- 密度行列はどうしてあるか…。量子力学では、純粋状態と言うものがあり、また、純粋状態がある割合で混ざった混合状態と言うものもある。この混合状態は、状態を並べて、それぞれに、確率を割り当てる、と言う形で記載できるが、これだと、2本のベクトルで書ける。物理学において実験的に観測をすると、物理量がこれこれの値をこれこれの確率で取る、と言う形で観測される。しかし、この観測される分布は、色々な混合状態に対応していて、区別ができない。区別するにはどうするか、と言うと、密度行列として表すことで解決する。解決すると言うことは、2本のベクトルで書けていたものが、正方行列に相当するたくさんの情報を持つものとして表して区別すると言うことである。しかし、物理観測では、区別がつかないので、この区別されて異なる密度行列から、同一の確率分布が観察されるべきである。この情報が落ちてしまう、観測確率が
である。区別されるべきだが、観測するとトレースしかわからない、と言うところで情報が落ちている
- 密度行列はnxnなので情報量は多いが、ランクを考えると、ランクが1のこともあるし、nのこともある。ランクが1の行列は、成分数こそnxn個あるが、n次元ベクトルのouter積になっているもののことであるから、n個の値で決まる。このような密度行列は純粋状態に対応する密度行列になっている、と言う性質もある
- 密度行列とはそんな役どころのもの(らしい)
- *-代数とその上で定義された状態の組
- 代数的確率空間
- 2 量子分解
- 実確率変数について考える。モーメント列が得られた時にどうするかと言う話
- モーメント列を扱うための「直交多項式」があると便利
- ベクトルの集合から直交ベクトル集合を作る方法にグラム・シュミットの直交化法こちらがある。順番に単位ベクトルを作る、次の単位ベクトルを作るにあたって、それまでに登録された単位ベクトルと直交しない成分を差し引くことで、「残り成分」を追加するべき単位ベクトル方向にする、と言う方法である
- これを関数について行えば、直交関数集合が取れる
- 直交多項式は、ヤコビ係数列と呼ばれる二種類の係数列に情報を持たせることができるのだが、そのヤコビ係数列が「きれい」な直交多項式にチェビシェフ多項式と呼ばれるものがある。これは三角関数の位相を整数倍した関数が、位相1倍の三角関数の多項式となっていることを示した多項式で、ヤコビ係数列がキレイ
- ヤコビ係数列
は、次の3項間漸化式の係数でもある
は期待値で、
は分散になってもいる
- モーメント列から確率測度・確率密度を逆算するのは、一般に大変。な、の、で、うまく逆算できるものを作って見ようと考えてみる。モーメント列そのものからの出発もちょっと面倒なので、モーメント列とヤコビ係数列とが1対1対応であることを利用して、ヤコビ係数列から確率密度を逆算してみる。さらに、制約を課して、ヤコビ数列の自由度をぐいっと抑えてやることにする。その例として、平均を0に指定(ここをパラメタ指定することもあるようだ)、分散には自由度を与えて指定、(したがって、ヤコビ係数列の第1成分がそれぞれ決まる)、その上で、ヤコビ係数列のそのほかの値は、一定にする(自由度2)。このような制約のきついヤコビ係数列に対して、決まる確率密度分布が自由マイクスナー分布。結局、分散pと、ヤコビ係数列の大多数の値を固定的に指定するa,qとの3変数(平均をパラメタ指定する場合は4変数)で決まるのがマイクスナー分布(参考)
- 相互作用フォック空間というものが出てくる
- 2つのヤコビ係数列が両方、登場する関係、というような意味合いで「相互作用」と称するのだと思う
- そもそも、ヤコビ係数列は、モーメント列を扱うにあたって登場した関数列
から直交関数列
を作ることと関係していた
- 今、ヒルベルト空間に正規直交基底を取ることを考える。このヒルベルト空間正規直交基底は、ヤコビ数列と関係する。直交基底のそれぞれはベクトルのようにも見えるし、(無限次元)ヒルベルト空間だと、関数のようにも見える。直交関数列なら、
もそうだったから、このヒルベルト空間に取らんとする正規直交基底は直交関数列
と関連の深いもののように見える
- このヒルベルト空間正規直交基底の要素間の関係をヤコビ係数列を用いて結びつけるにあたり、3つの線形作用素
を用いれば良いらしい。その時に気にするのは、
が関係する
- いずれにしろ、ヒルベルト空間正規直交基底が、ヤコビ係数列に3つの線形作用素を追加することで得られ、それは、モーメント系列のための直交関数列の影武者のような存在だと言えそうだ
- 実際、この直交関数列
とヒルベルト空間の正規直交基底は「等距離作用素」と呼ばれるもので対応づけされる
- 結局、ヤコビ係数列が与えられた時に、そこから、ヒルベルト空間と、正規直交基底と、3つの線形作用素(生成作用素と消滅作用素と保存作用素という名がそれら3つにはついている)
- 正規分布やベルヌーイ分布などが、この相互作用フォック空間に「真空ベクトル(ヒルベルト空間の正規直交基底の第1基底)
」を組み合わせて得られる「相互作用フォック確率空間」の例になっている
- ただし、単純な実確率変数の場合2つのヤコビ係数列のうち、片方は0で、もう片方も、ごく単純(1,2,3,...,とか、0,1,0,1,...とか、1,1,1,1...とか)
- 3 代数的グラフ理論
- 隣接行列
- 隣接行列を置換行列でサンドイッチすることは頂点IDの付け方の変更に相当し、グラフとしては同一のものを表している
- 隣接行列の冪乗に係数をかけて足し合わせてできる行列全体は隣接代数をなす→行列の冪を考えてモーメントを取るあたりで、量子確率的
- 隣接行列は特性多項式を持つ
- パスグラフというのは、1本道状のグラフ。パスグラフの長さを伸ばしていくと、グラフの系列ができるが、それに対応して特性多項式の系列もできる。このパスグラフの特性多項式の系列は第二種チェビシェフ多項式を用いて表現できる
- グラフは行列で、それが直交多項式と関係する
- 量子確率論では、行列からモーメント列が出て、直交多項式があり、ヤコビ係数列が出てきた。その関係と絡んでくる話をしているのだと思われる
- 4 スペクトル・グラフ理論
- グラフのスペクトルは、隣接行列の(正の固有値)の昇順列と、それぞれの固有値の個数のベクトルとのペアで表すことが多い
- グラフの固有値のところにデルタ関数があるとみなせば、グラフのスペクトルは、デルタ関数がぽつぽつと立った「確率分布」となる。これがスペクトル分布
- スペクトル分布を代数的確率空間で扱うことが論じられる
- 代数的確率空間では、ヒルベルト空間直交基底を使って議論したが、それは、グラフのある頂点をヒルベルト空間直交基底の一つの基底である真空状態ベクトルに対応させたときに相当し、モーメントが定まる。このモーメントは、指定した頂点を出発して自身に戻る歩道の個数になっている
- グラフの隣接行列、そのべき乗が作る接続代数が何を表しているかというと、真空状態を基点とした、ヒルベルト空間直交基底が、グラフ距離ごとに頂点をグループ分けすることに相当し、
的な表現と対応する(らしい)こと
- このようなグラフのスペクトル分布を量子確率空間的に扱い、グラフを分解して考えることは、規則的なグラフにおいてその漸化式や、真空状態、ヤコビ係数列が調べられている。
推定。パラとノンパラ
- 混交正規分布が背景にあるとする
- パラメトリックに、単純な正規分布を仮定して、推定すると、サンプル数を増やしても、推定結果は1峰性の正規分布であり、背景分布の平均(期待値)と分散は正確になるが、混合正規分布の特徴である複数峰は決して推定されない。
- また、期待値と分散の推定値は、散布する数が少ないときから安定して、よい値が推定される
- この、サンプル数が少ないときから、(モデルとしては不十分ながら)推定結果がよいことを、推定のバリアンス(ばらつき)が小さく収まるという
- その一方で、サンプル数をどんなに増やしても、真の分布である複数峰には近づかないことを、「モデルが真からずれている」から「推定結果もずれざるを得ない」と言う意味で、バイアスが大きい推定になっている、と言う
- 他方、ガウシアン・カーネルによる密度推定では、個々のサンプルに小さな正規分布を担わせ、それらの加算として、全体の密度分布を推定させる。したがって、サンプル数が大きくなればなるほど、たくさんの小正規分布の和として分布推定される。使用するパラメタ数が大きくなるともいえる
- この、サンプル数が増えれば増えるほど、分布を説明するパラメタ数が大きくなる推定法であることを「ノンパラメトリックな推定手法」である、と言う。
- しかしながら、個々のサンプルに担わせる小さな正規分布をどんなものにするかに選択の余地があり、その選び方で結果が変わる。ガウシアンカーネル法の場合には、平均は観測値そのものとするとして、分散をどうするかは選ばないといけない
- その分散を大きくしすぎると、背景分布の細かい多峰性は表現できないし、分散を小さくしすぎると、全体の様相をつかみ損ねて、標本依存性が上がる。この標本依存性が上がってしまうことを、オーバーフィッティングと言ったり、推定のバリアンスが大きいと言ったりする
- しかしながら、パラメトリックな手法の際に、バイアスは大きくてもよいからバリアンスを小さく維持することに成功したことの裏返しで、バリアンスは大きくなるが、バイアスは小さくできる。したがって、標本数が大きいときには、標本数がバリアンスを押しとどめてくれるので、バイアスの小さい、真の分布に近いものを得うる、という可能性をもつ
- 以下のRコードは、4峰性の1次元混合正規分布に対して、単純な1峰性正規分布推定をパラメトリックな推定法の代表として用い、ガウシアンカーネル法をノンパラメトリックな手法として用いつつ、ガウシアンカーネルの個別分布の分散に大小2つを採用することで、サンプル数の多寡による推定分布の変化の様子を見ている
- Nが小さくても大きくても、1峰パラメトリック推定(赤)は大して変わらない・・・バリアンスが小さい
- Nが小さいときと大きいときでも、緑の推定(ガウシアンカーネルで分散が大きめ)は滑らかな推定分布であるが、方や、中央付近に大きな1峰、方や、中央付近に2峰の可能性の萌芽が見える
- 分散の小さいガウシアンカーネルの場合は、Nが小さくても、大きくても、中央付近にシャープな2峰が推定できている点では、よい推定だが、Nが小さいときに、左右の裾領域に複数の峰が現れており、真分布に合致せず、標本に引きずられている様子が見える(バリアンスが高い)
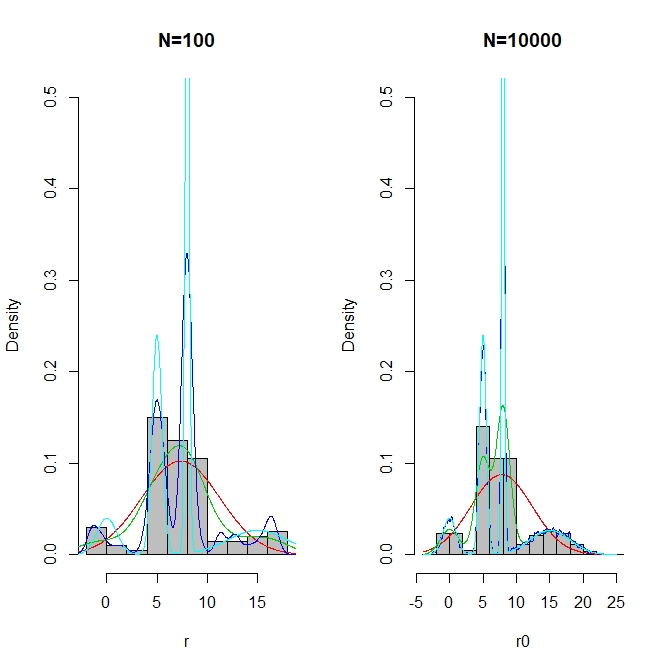
モザイク・キメラ・混合試料のための二項分布Rコード
- シークエンサーを使ったSNPタイピングをDNA鑑定に用いるとき、単純なホモ・ヘテロ接合体の分離だけでなく、モザイク・キメラ体個人のそれをする必要に迫られることになる
- さらに、この課題は混合試料の解析・解釈とも関係する
- それを考えるためのスライドがこちら
- スライド作成に用いたコードが以下
ぱらぱらめくる『Nature Reviews Genetics』2019
- 毎年やっている、年末の『パラパラめくるNature Reviews Genetics』
- 今年もやってみましょう
- 年を経るごとに、細かいことは、ま、いいか、と、雑になっていますが、頑張って参ります
- 全体の印象としては:
- 昨年までなどは、「現象」に関する総説が多かったように思いますが、今年は「将来を志向した概念」に関する記事がめだったように思います。
- 短文紹介した記事はどれも面白いと思います。それ以外にも面白いものがありましたが、「医学」「データ解析」系に興味が強いので、志向方向が近い方は取り上げたものをめくってみると楽しいのでは、と思います。
- 2019 Dec
- 2019Nov
- 2019Oct
- ゲノム上にある遺伝子とその制御構造の1次元構造位置と核内3次元構造の知見が増えてきており、3次元構造が遺伝子の協調制御に大事だろうと思わされるが、あえてそれを改変してやっても、細胞は機能を維持するらしいという話。たまたま見えているゲノムパーツの3次元構造と、必要に迫られて形成される3次元構造。ニワトリと卵の話は、技術が進んでもなかなかゴールに達しないようです
- 2019Sep
- 生命現象の本質は、離散的な要素(細胞しかり、個人しかり)って、それぞれが活動しその総体として表現型を形成するという仕組み。そのように考えたとき、個々の要素のばらつきとその確率的振る舞いは、本質的な意味を持つ。そんな側面に関するお話
- 2019August (ピックアップ文章なし)
- 2019July
- 2019June
- Clinical metagenomicsは「個人が生まれながらに持っているDNAセット」とは別だが、個々人がもれなく持っている膨大な影響を与える遺伝子群についての臨床応用の話。疫学で環境要因とみなしていたもののどれくらいが、メタゲノム的には環境要因扱いとなり、遺伝形式不明かつあやふや度の強い遺伝要因扱いとなっていくのかは(リンク先ペイパーとは別の意味で)興味深いです
- 2019May
- 2019April
- 2019March
- スプライスバリアントは(同一の)遺伝子が発揮する分子多様性の初期段階要素。それについてAIを使って、どんなバリエーションが出るかという検討の話
- 男女差。ポリティカリーには「男女平等」だけれど、遺伝学的には、かなり峻別度が高い(完全に峻別はできないけれど)情報であることは確か。その男女差に着目して様々な点から現在の(分子レベルの)遺伝的現象を概説
- 2019Feb (ピックアップ文章なし)
- 2019Jan